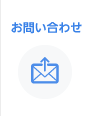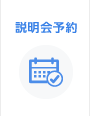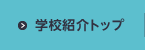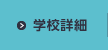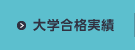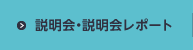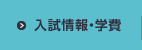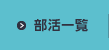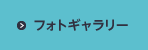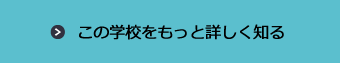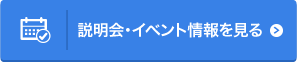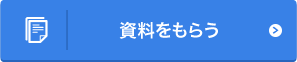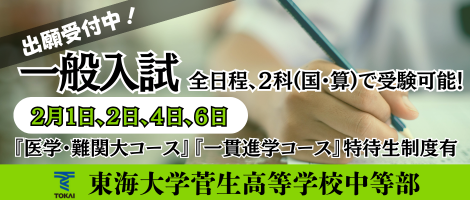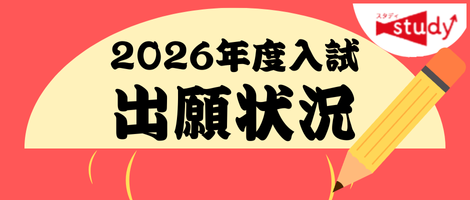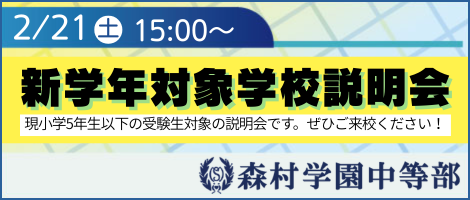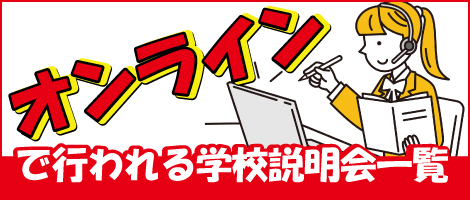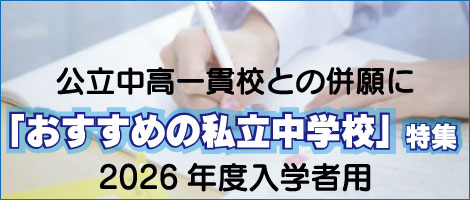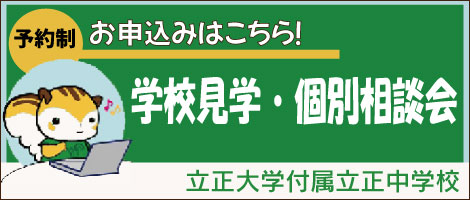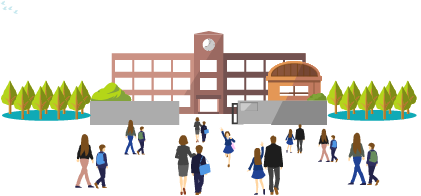スクール特集(帝京中学校の特色のある教育 #1)

中学3年間は非認知能力の育成を重視! 中高一貫「インターナショナルクラス」
帝京中学校では、2025年度に中高一貫「インターナショナルクラス」を新設。クラスの特色について取材した。
同校では、1998年に高校の「インターナショナルコース」がスタート。英語学習と探究学習を掛け合わせた独自プログラムで、国際社会で活躍できる人材を育成している。その経験を活かし、2025年度に一貫進学コース「インターナショナルクラス」を中学校に新設。クラスの特色などについて、「インターナショナルコース」主任の関陽平先生に話を聞いた。
中高一貫教育の「インターナショナルクラス」始動
5年前に「インターナショナルコース」の主任に就任した関先生は、留学制度や探究プログラムなどの改革を進めてきた。その成果もあり、「インターナショナルコース」への内部進学を希望する生徒が増えてきたという。
「高校のインターナショナルコースには、英語力の高い生徒たちが外部から入学してきます。一貫進学クラスや一貫特進クラスで行っている英語学習だけでは十分でない面もあり、高校のインターナショナルコースで存分に力を発揮するための土台をしっかりと作れる環境を整えたいと考えていました。内部生の希望者が増えてきたこともあり、6年間の一貫教育としてインターナショナルコースで学ぶ生徒たちを育ててみたいという思いを形にしたのが、インターナショナルクラスの新設です」(関先生)
高校の「インターナショナルコース」では、約7割の生徒が難関私大を目指し、近年は、海外大学へ進学する生徒も増えてきている。
「インターナショナルコースの約7割が、早慶上智、ICUを第1志望にしています。近年は、学年で2、3人は海外大学へ進学するようになりました。主にオーストラリアの大学ですが、3ヶ月留学などを経験して、オーストラリアに親しみを感じているからかもしれません。海外大学への進学と関連した制度としては、DDP(希望者を対象とした、同校の卒業単位と同時にアメリカの高校卒業単位が取得可能なプログラム)やUPAS(海外大学進学協定校推薦制度)も利用できます」(関先生)
しかし、同コース(クラス)の特色は、英語を強みとした受験にこだわらず、日英バイリンガルとして両方の運用能力を育み、あらゆる選択肢が残せるカリキュラムになっていることだという。
「このコース(クラス)のゴールは、英語という言語の習得ではありません。自分のゴールを叶えるためのツールが言語であり、それが英語か日本語かは入学時にはまだわからないのです。英語や一部の教科はオールイングリッシュの授業ですが、学年が上がってもすべてがイマージョンになるわけではありません。理系の授業もありますし、一般選抜にも対応できるようにカリキュラムを組んでいます。海外大学へ進学するための活動歴や英語力を積み重ねていきますが、途中で進路変更して日本の大学を受験することも可能なのです。ですから、コースとして、こんな進路を目指してほしいという目標は立てていません。国内外、総合型選抜や一般選抜も含めて、あらゆる可能性を残しています。6年間でやりたいことは変わるでしょうし、変わったときにどのような変更にも応えられる学校でありたいと思っています」(関先生)

▶︎インターナショナルコース主任 関 陽平先生
中学3年間で伸ばしたい「非認知能力」
中高一貫の同コースでは、中学校での3年間は非認知能力を大切にしているという。「グローバル・リーダーシップ・プログラム」と呼ばれる独自の探究プログラムを通じて、主体性やコミュニケーション能力といった非認知能力の育成に取り組む。その中でも、最重要コンピテンシーに位置づけているのがリーダーシップだと関先生は語る。
「中学3年間はテストの点数や校内順位といった目先の結果に一喜一憂するのではなく、いろいろな人と交流しながら、リーダーシップを発揮したり協調性がとれるようになってほしいと考えています。そこをグランドデザインとして置いて、様々な機会やプログラムを用意しています。大学受験では他校の生徒と競うことになりますし、社会に出ればいろいろな年代と競うことになるでしょう。ですから、校内順位に満足しているようでは、それ以上伸びないと思うのです。学校行事なども生徒がリーダーシップを発揮する機会として考えていますし、課外活動での取り組みなども大切にしてほしいです」(関先生)
「グローバル・リーダーシップ・プログラム」の集大成として中3で実施するのが、「シンガポール探究研修」(原則全員参加)だ。現地の大学や企業と連携し、社会課題について学び、問題解決に向けた議論などを行う約1週間の探究研修となっている。
「中1、中2で行う探究学習は、テーマやメンバーを変えて議論や調査を繰り返します。そこで培った力を、初めて会う現地の大学生や社会人に対して英語を用いて発揮する機会となるのがシンガポール探究研修です。リーダーシップをはじめとする非認知能力をどれだけ発揮して、議論して答えを出せるかを試す機会となります。中1から学んできたことの集大成として、身につけた力を全部出して挑んでほしいです」(関先生)
個々に応じた形の「リーダーシップ」
リーダーには様々なタイプがあり、「グローバル・リーダーシップ・プログラム」でも生徒全員に「先頭に立って引っ張る力」を求めているわけではない。個々に応じた形でリーダーシップを発揮すればよいが、受け身であることをよしとする教育は同クラスではしていないという。
「このクラスでは、人の指示を聞いて従える人が優等生ではないのです。傾聴を重んじたり、コンセンサスを取るために動くなど、どのような形でもよいので、自分に合った形でリーダーシップを発揮してほしいと考えています」(関先生)。
同校では、8年ほど前から「模擬国連」に挑戦している。「インターナショナルコース」(高校)の生徒が、大会に挑戦したいと言ったことがきっかけで取り組みを始めたという。「模擬国連」では、生徒が各国の大使になりきって、英語を用いて議論を行う。時には他校の生徒や海外の生徒とも議論を行って社会課題について考えながら、英語という共通言語のスキルを高め、自らの世界と学びを広げていくことを目指している。
「大会で日本を代表する進学校の生徒たちと交流すると、高校生の段階で社会に対して関心を持ち、ボランティアや起業などにも強く関心を持っていると感じます。2023年に当時最年少の26歳で当選した芦屋市長も、全日本高校生模擬国連大会で最優秀賞の受賞経験があり、早くから教育問題に関心を持っていました。私自身が高校生の頃は社会に対してそれほど関心を持っていませんでしたし、私たち世代は大多数の高校生が同じような状況だったでしょう。しかし、模擬国連で上位校となる生徒たちを見ていると、これから社会を引っ張っていく、あるいは社会を変えてくれるのは、彼らや彼女たちのような人なのだと感じます。本コース(クラス)では、そのような生徒を育てていきたいと思っていますし、将来、社会を動かすような人材を輩出できたら、教員としてこれ以上ない喜びです」(関先生)
「インターナショナルクラス」の生徒にインタビュー
Aさん 中学1年生 (4歳頃から中学受験前まで香港で生活し、現地日本人学校に通学)
Hさん 中学1年生 (カナダで生まれ、7歳頃までカナダで生活)
――この学校を受験した理由を教えてください。
Aさん 帝京の「インターナショナルクラス(コース)」の教育制度に魅力を感じて、兄と同時に入学しました。僕は英語が得意なので、学校でもたくさんの人と英語で会話をしたいと思っています。「インターナショナルクラス」は、英語の授業のほかに英会話の授業があったり、放課後講座などで英語を話す機会が多いのでいいなと思って受験しました。
Hさん 新しくできた「インターナショナルクラス」は英語を重視しているので、友達と一緒に楽しく英語を話せたらいいなと思って受験しました。

▶︎Aさん
――英語の授業はどうですか?
Aさん 授業では、ロールプレイやプレゼンを英語で行うこともあり、先生やクラスメートと一緒に英語で話せるので、とても楽しいです。
Hさん 英会話の授業は希望制で取り出し授業を受けられるので、ラウンジで取り出し授業を受けています。英語の授業は、今のところ自分が理解できている範囲なので、友達がわからないところがあると助けたり、教えたりするのが楽しいです。

▶︎Hさん
――昼休みのランチミーティング(少人数でネイティブ教員と英会話)では、どんな話をしましたか?
Aさん 毎回テーマが決まっています。僕が参加したときは、住んでいる地域についてなど、先生や友達と一緒に英語をたくさん話せて楽しかったです。
Hさん 私はこれまでに、3回参加しました。全部テーマが違っていましたが、自由な時間があったらどんなことをするかというテーマが印象に残っています。1時間、1日、1ヶ月という3つの場合について、いろいろと想像しながら話せて楽しかったです。私は作品をつくるのが好きなので、1ヶ月も自由な時間があったら大きな絵を描きたいと考えました。1日目は何をして、2日目はどこまで進めるかなど、1ヶ月間の計画を立ててみたのです。授業と違って、いろいろなテーマについて楽しく話せるのがいいなと思います。

▶︎ランチミーティング
――他国で暮らした経験があるからこそ感じられることはありますか?
Hさん 他国に住んだことのある人は、世界の見方や文化に対する考え方などが住んだことのある国の数だけあるので面白いと思います。例えば歌を訳すとき、ピッタリの言葉がないことがあります。「music」という単語なら「音楽」というように訳せますが、「ケセラセラ」という歌詞を日本語に訳そうとすると、メロディーに合うようにピッタリと訳せる言葉がありません。それぞれの国で訳された歌は完全に同じ意味ではないこともあるので、2つの国で暮らしたことのある人は2つの世界観を知っているので面白いなと思います。
――将来の目標などはありますか?
Aさん 他の人を助けられるような人になりたいです。人はそれぞれ得意なことと苦手なことがあるので、協力し合った方がよいと思います。例えば、授業でわからないことがある友達がいて、自分は理解できていたら、教えてあげたり、助けてあげたいです。
Hさん 小学生の頃、目標にしている先生がいました。私にとって日本語の学習は難しかったので、先生にたくさん質問をしましたが、何回質問してもその先生は優しく教えてくれたんです。その先生のように、誰に対しても嫌な顔をせずに、苦手だなと思う人がいたとしても、同じ態度で人を助けることができる人になれたらいいなと思っています。
<取材を終えて>
関先生が例として挙げていた芦屋市の高島市長は、当時の箕面市長を表敬訪問した際に、小学校で出前授業をしたいと相談したという。そしてそれが実現し、生徒会のメンバーと共に箕面市内の小学校で出前授業を行い、その後は神戸市内の学校にも活動を広げていった。関先生へのインタビューを通して、同コースでそのような人材を育てたいという熱い思いが伝わってきた。同校の模擬国連への取り組みについても、ぜひ注目していただきたい。