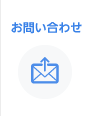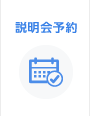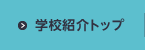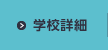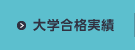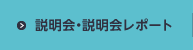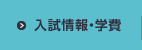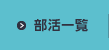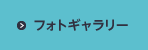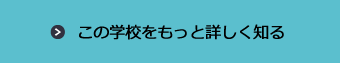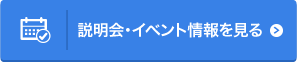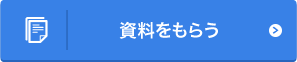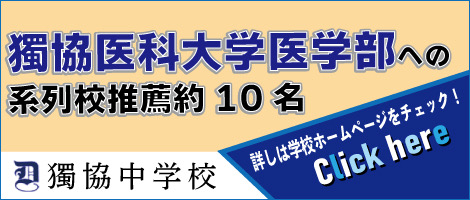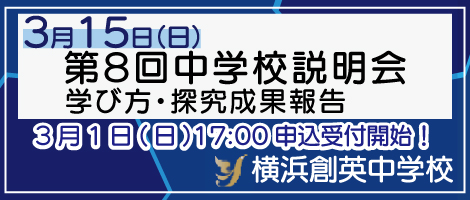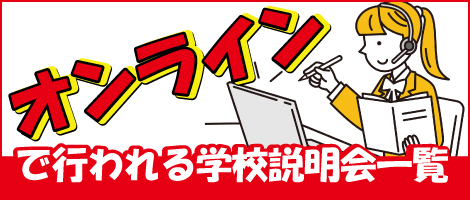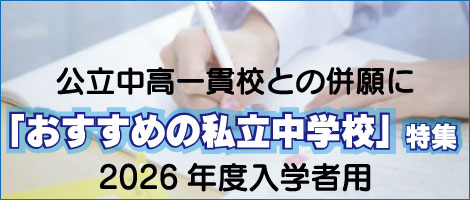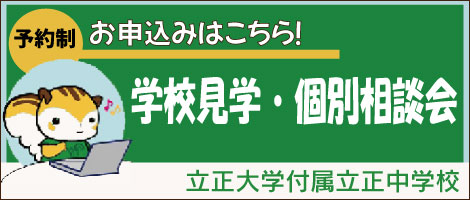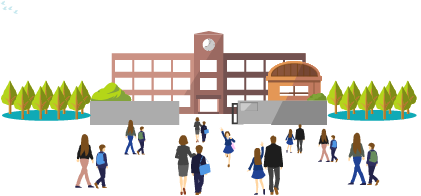スクール特集(東京成徳大学中学校の特色のある教育 #5)

「ICT教育」「海外留学」「探究活動」を柱とし、社会で活躍できる力を育成
東京成徳大学中学・高等学校は、「未来を見据え、世界を知る、自分を拓く」を教育テーマに、どんな社会でも対応し、活躍できる人材の育成を図っている。同校の教育活動を取材した。
同校は将来、生徒たちが変化の大きい社会にも柔軟に対応し、生き抜いていくために、6年間の教育を通して、「創造性」「主体性」「チャレンジ精神」を備え、「自律した学習者(Distinguished Learner)」へ成長することを目指している。その実現に向け、1.ICT教育(創造性を育む教育)」、2.海外留学(チャレンジ精神を育む教育)、3.探究活動(主体性を育む教育)の3つを重点項目に設定。それぞれの教育の特色や、培った力を未来につなげる進路指導について、教頭で入試広報部長の和田一将先生に話を聞いた。

▶︎教頭・入試広報部長 和田 一将先生
ICTを活用し、創造性を伸ばす「未来を見据えた学び」
「本校は、生徒たちの“自ら考え、社会で活躍できる力”を養うために、『未来を見据え、世界を知る、自分を拓く』ことを教育のテーマに設定しています。1つめの『未来を見据える』教育では、生徒が1人1台所有するiPadなどのICT機器を、授業や校外学習、行事、委員会などいろいろな活動に取り入れ、活用することで、創造性を育てることを目指しています。また本校は、ICT教育の取り組みにより、Apple Distinguished School(ADS)の認定校にもなっています」と和田先生は言う。
ADSとは、Appleが国際的に教育効果の高さを認定している学校で、世界37か国で889校、日本国内では16校、東京都内の私立中高では同校を含め3校のみが認定されている。ADSは3年ごとに見直しがあり、学校のビジョンや教育目標がカリキュラムに反映されていること、授業実践の成果を証明することなどが求められるという。同校には、和田先生を含む5人のApple Distinguished Educator(ADE:Appleのテクノロジーを使い、教育現場の変革に取り組む教育者)が在籍し、ICTを活用する授業を研究している。
「たとえば、私の英語の授業では、中学2年生が英語を使って、新1年生を迎え入れるためのムービーを作りました。また、数学の授業で二次関数を学習した後、ARで曲線を描いたり、歴史の授業では、織田信長のような武将を取り上げ、インタビュー形式で歴史を学ぶ番組を制作したりしました。オーストラリアの学校とオンラインでつなぎ、双方で画面上にクイズを出して、学び合いをしたこともあります。
ICTを活用して新しいものを創ったり、表現するには、その前提となる知識が必要になります。相手に伝えるための思考や判断する力なども求められますね。ほかにもICTの利点は、生徒たちが主体的かつ協働的に学べることにもあります。
また、本校がADSの認定校ということで、イスラム圏からの学校の生徒が見学に来たこともありました。ADSでは、公平性や多様性をもって、どんな子どもも尊重され、イキイキと学ぶことが大切にされています。テクノロジーを使いながら、いろいろな国の人たちと交流をしたり、価値観を共有できるのも、生徒にとって良い経験になります」と和田先生。
さらに同校は、プログラミング教育にも力を注いでいる。中学生からコーディングを学び、ロボットの制御や簡単なゲームを作ったり、高校では東京工科大学と連携し、大学の先生の講義を受け、アプリの制作なども行っている。

中学生全員が海外留学を体験! 世界を知り、チャレンジ精神を育む
「世界を知る」教育として、同校は中学課程に海外留学のプログラムを2つ用意している。
「1つめは、2年生全員によるフィリピン・セブ島の2週間語学研修です。GLCという語学学校の施設に宿泊し、月曜から金曜日は朝から夕方まで、マンツーマンやスモールグループで英語のレッスンを受けます。土日は海へ行くなどアクティビティに充て、日本人が経営する孤児院を訪れるスタディツアーも行っています。そこで生徒たちは美しい海のあるリゾート地と、スラム街というセブ島の2つの側面を知ることになります。
孤児院には、人身売買される寸前で保護された子どもや、満足に食事のとれない貧困家庭の子どもなどが暮らし、教育を受けています。生徒は初めて見る世界に衝撃を受けますが、現地の子どもたちとの交流を行うこと、また、彼らが明るく前向きに生きている姿を見て、多くの気づきを得るようです。孤児院の訪問自体が支援にはなっているのですが、『ペアを組んだ子に靴を買ってあげてください』と、自分のお小遣いから3000円を孤児院に寄付した生徒もいました」と、和田先生は話す。
「2つめは、中3の3学期に、約3か月間ニュージーランドに留学するプログラム(選択制)です。本校で20年以上続いているプログラムで、生徒はホームステイをしながら現地校に通います。ニュージーランドは移民も多く、人種や宗教もさまざまで、多様な価値観に触れることも、留学の大きな目的です」
なお、ニュージーランド・ターム留学を選択しない場合は、国内グローバルカリキュラムとしてプロジェクト型の学習などを行っている。また高校でも、3ヵ月、6ヵ月の留学プログラムを新設する予定だ。
「海外留学は、語学力の向上はもちろん、親元を離れて違う環境で生活することで、自律心を養います。多感な時期にいろいろな体験をしたり、価値観を知ることは、視野を広げ、同時に自分の枠も広げていきます。生徒たちには新しい可能性に向けて、どんどんチャレンジしてほしいと願っています」

▶︎セブ島語学研修

▶︎ニュージーランド留学
主体的に学ぶ探究活動で、自分の未来を切り拓く
「自分を拓く」教育は、「探究型学習プログラム」として、主に高校で展開している。生徒たちは中学でセブ島短期語学研修やニュージーランド・ターム留学を経験し、世界の広さや多様な価値観を理解したうえで、自分のやりたいことや進路を見出していく。そのためのプログラムだ。
まず4年(高校1年)次では、「Diversity Seminar(ダイバーシティ・ゼミナール)」という総合探究の授業を実施。生徒たちは多岐に渡る専門分野から自分の興味あるテーマを選択し、1年かけて個人やグループで探究活動を行う。今年度は、「人と自然とのかかわり」「芸術の可能性を探ってみよう」「美味しい珈琲を淹れよう」「もったいないをサイエンスしよう」「医療ゼミ・ひとを支えるを考えよう」「アプリを開発しよう」「コミュニケーションマジックゼミ」の7つの講座が開講されている。
「『人と自然とのかかわり』のゼミでは、東京湾で釣った魚を解剖してマイクロプラスチックの有無を調べるなど、実地調査をしながら人間の営みと自然環境保護の両立の可能性を探りました。『芸術の可能性を探ってみよう』は、音楽や陶芸、手芸などの創作活動を行い、『美味しい珈琲を淹れよう』は、実験を通して科学的に美味しいコーヒーの淹れ方を研究します。『もったいないをサイエンスしよう』は、生ごみを堆肥化したり、大学の先生の講義を受けてリサイクルシステムを考察したりします。『医療ゼミ・ひとを支えるを考えよう』は、医療現場の体験やケーススタディを通じて、人が支え合うことで成り立つ社会のシステムを考えます」と和田先生は説明する。
5年(高校2年)生になると、自分でテーマを決めて、個人研究に取り組む。その一環で、設定した課題の調査や仮説を検証するために、「実地踏査型研修旅行」を実施している。旅行先はその学年の研究内容によって変わり、昨年度は関西と沖縄の2ヵ所が拠点となった。沖縄では米軍基地や海の生物を調べたり、関西では京都の甘味処を巡って関東との違いを記録するなど、ユニークな調査をする生徒もいたという。
「この研修旅行では、調査の計画や行程も生徒が考えます。旅行後は、自分なりに結論を考察し、最後に論文にまとめます。1年に及ぶ個人研究は、まさに主体的な学びの集大成です。こうした探究活動は、自分の将来を考えるきっかけになり、実際に進路に結び付けていく生徒もいます。
ある卒業生は、中学でのニュージーランド留学を経て、4年生のゼミではSDGsと社会貢献について学び、5年生ではLGBTに関する論文を書きました。それだけでなく、LGBTの問題に関心を持ってもらうために、グッズを作って販売し、団体に寄付をしていました。卒業後は東京外国語大学に進学し、将来は様々な人が活躍できる社会を作っていきたいそうです」と、和田先生は1人の女子生徒の歩みを紹介する。

▶︎ダイバーシティ・ゼミナール

▶︎実地踏査型研修旅行
多様な進路や入試に対応し、1人ひとりに合った進学をサポート
同校は、高校卒業後の進学を、自分の未来に向かう重要なステップと位置づけて、手厚くサポートしている。
和田先生によると、「年に2回、1週間の進路指導週間を設け、大学の講師や社会人を招いて、講座を開いたり、キャリアインタビューなどを行っています。また、私たちは進学指導を、大学名ではなく、生徒が自分のやりたいことに挑戦することを大事にし、一人ひとりに合ったサポートをしています。今は、志望する進路も入試方法も多様化しています。そのため6年(高校3年)次は、担任と、その生徒が希望する進路に強い教員が受験指導をする『W担任制』をとっています。また、各生徒の成績を分析し、指定校推薦ができるのか、このボーダーを超えたなら一般選抜を勧めようなどと、複数の教員で対策を練っています」と話す。
「ここ数年は、海外大学に進学する生徒も増えています。ある卒業生は映像を専門に学べる国内大学を探していたのですが、希望する大学が見つからず、カナダの大学に進学しました。国内大学において、本校は高等部と併せて約1320名分の指定校推薦入学枠を持っていますが、近年は海外大学の指定校推薦枠も50校ほど確保しています。
また、海外留学や探究活動での学びを活かして、総合型選抜で受験する生徒も多くなりました。6年では選択科目として小論文の授業を実施したり、志望理由書の書き方も指導しています。もちろん一般選抜においても、講習会や個別補習を設けて、それぞれの生徒に応じた学習支援を行っています」
このように同校では、6年間の学びで培った力を進路につなげるサポートを行い、これからのグローバル社会で活躍できる人材を育成している。
<取材を終えて>
和田先生によると、ここ数年、同校に進学する生徒の傾向として、教育方針や海外留学、ゼミといったプログラムをしっかり調べたうえで受験し、第一志望で入学する生徒が増えているという。実際に、同校を気に入って入学し、一つひとつのプログラムを消化して、やりたいことを見つけた生徒は、希望の大学に進学しているそうだ。卒業生の進学実績を見ても、6年間の体系的な教育プログラムが成果を出していると言える。