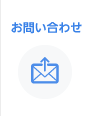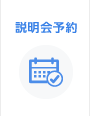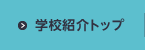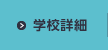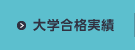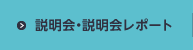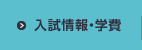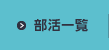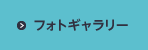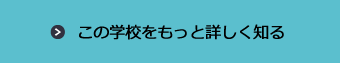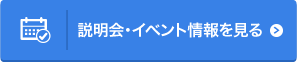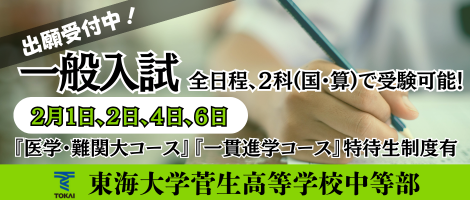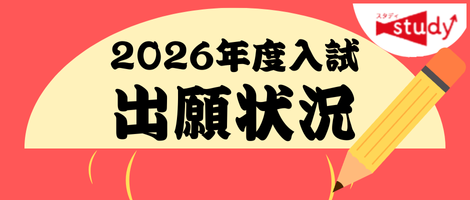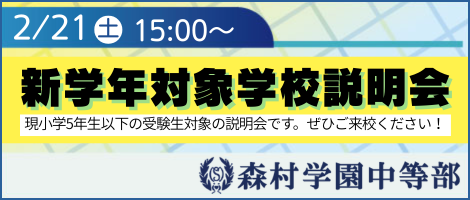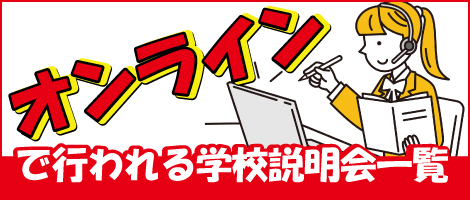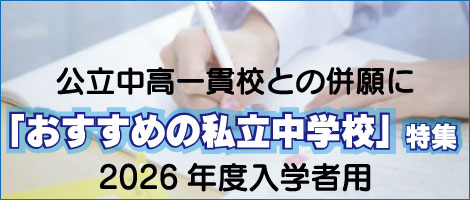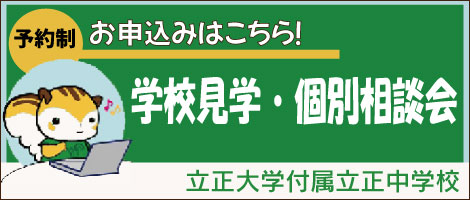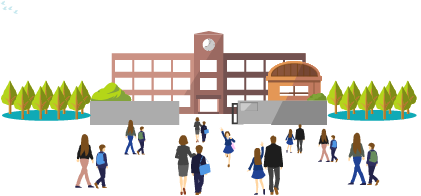スクール特集(吉祥寺学園中等部の特色のある教育 #3)

インクルーシブな環境で多様な価値観を尊重し、 一人ひとりの個性と可能性を伸ばす
インクルーシブ教育のパイオニアである武蔵野東中学校は、2026年4月に吉祥寺学園中等部に校名を変更する。その理由や教育の特色などについて、校長の林武宏先生に話を聞いた。
インクルーシブ教育を通して、努力する姿勢や自己肯定感を育む
同校の母体である吉祥寺学園は、1964年に幼稚園、1977年に小学校、1983年に中学校を開校し、創立以来、定型発達児とASD児が共に学ぶインクルーシブ教育を実践している。林校長によると、「ユネスコがインクルーシブ教育を提唱したのが1994年です。本学園はそのはるか以前より半世紀にわたり、多様な価値観を尊重し、誰もが共に生きる社会を学校の中に形成してきました。いわばインクルーシブ教育のパイオニアでもあります。また、本校は上級校として普通高校を併設していません。私たちは13~15歳の3年間を著しく成長する時期と捉え、伸びる時期にきちんと伸ばす教育を行いたいと考えています。その後の進路である高校の受験対策も、万全の態勢を整えています」と語る。
「一方、世の中に目を向けると、近年は少子化が加速しています。それに伴い、全国で毎年平均約400の学校が閉校しており、学校も淘汰される時代になってきました。本校においても、核となるインクルーシブ教育や3年間で人間力を伸ばす教育は継続しながらも、より価値を高める進化をしていかなくてはなりません。そうしたリブランディングの流れの中で、校名変更をすることになりました」
なお、同校のインクルーシブ教育は、カリキュラムとホームルームは定型発達児クラスとASD児クラスを分けているが、清掃活動や休み時間などの日常生活は共に過ごし、行事や校外学習もチームや班で協力をし合っている。林校長は、「定型発達児とASD児は目指す進路なども異なりますが、学校生活を共にするなかで互いに影響を与え合い、双方にとって自己肯定感を高め、ウェルビーイングを実感することができる相互作用をもっています」と話す。
「たとえば、縄跳びを1回跳ぶことも難しいASDの子が、何度も何度も練習を繰り返して跳べるようになります。その姿を見て定型発達の子たちは、『自分も勉強を頑張ろう、部活に励もう』と思うようになる。私たちはできることの客観的な価値ではなく、そこに至るまでの過程を大事にしています。それぞれの目標は違うけれど、目標に向かってまじめに一生懸命に取り組むことに価値を置き、頑張ったことをみんなで評価する。努力することが当たり前の雰囲気がこの学校にはあります」

▶︎校長 林武宏先生


外部からの評価も高い「英語教育」と「探究科」の活動
同校の教育の特長として、まずは実績のある英語教育が挙げられる。1つの基準になるのが英検取得率で、中学3年生は2024年3月時点において、3級以上が全体の98%、準2級以上が85%、2級以上も25%を占めている。ちなみに2級は高校卒業程度、準2級は高校中級程度、3級は中学卒業程度に相当し、3年生の4人に1人が高校卒業程度の英語力を持っているといえる。この英検取得率の高さが評価され、同校は日本英語検定協会より優秀団体賞【取得率部門】を6度も受賞しているという。
「本校は以前から英数を重視したカリキュラムを作り、習熟度別に3つのコースに分かれて少人数制の授業を行っています。中学で初めて本格的に英語を学ぶ生徒も、具体的な目標を持って学習できる内容になっており、ハイレベルな生徒は高校内容も含む高難度の学習に取り組んで、さらに力を伸ばしていきます。また、外国人講師とマンツーマンで会話をするオンライン英会話や、海外語学研修、英語スピーチコンテストを実施したり、授業以外でもネイティブ教員と触れ合う機会をたくさん作ったりして、4技能(読む・聞く・話す・書く)を満遍なく磨いていきます。そして英検取得率の高さは、先に述べたように、生徒が“目標に向かって常に努力している”ことも、成果として現れているのだと思います」と林校長は言う。
また同校は、2007年度から取り組んでいる「探究科」の学びにも力を入れている。「当初は、『研究活動』という名称で、教科横断のいわゆる課題解決型の学習を課外で行っていました。私も発案者の1人だったのですが、教科の枠組みがあると、どうしても学びが狭くなってしまいます。そこで、生徒自身がやりたいこと、解決したい課題を考え、その問いに対していろいろなルートからアクセスし、ゴールに向かうという活動を始めたのです。そして2018年度には、正課の授業にしました。その際、授業名を何にするか、先生が集まって話し合いをしました。今振り返っても、『探究科』という言葉を選んだのは正解でしたね」と林校長は話す。(注・文部科学省の学習指導要領による「探究」型の学習は、中学校課程は2021年度から取り組みを開始)
探究科の学習の流れは、中1で自然科学、人文、社会科学、創作の分野から興味のあるゼミを選択し、ゼミ活動を通じて探究の基礎を身につける。中1の12月から各自、探究のテーマを先生とカンファレンスをしながら設定し、中2より個人探究の活動を開始する。 11月の学園祭では全員がプレゼンをし、来場者の意見やアドバイスも参考にして完成度を高め、1月に再度、2年生全員がプレゼンを実施。その際に審査を行い優秀賞を決定する。
「18年前に研究活動を始めた時は手探りの状態でしたが、毎年内容をブラッシュアップし、今では学校オリジナルのテキストや思考ツールも使用して取り組んでいます。いつか外部のコンクールにも出せたらいいなと考えていて、成果も出てきたので2019年に試しに旺文社の『全国学芸サイエンスコンクール』に応募してみました。そうしたら3つの作品が入選したのです。旺文社の担当者から、『初年度に、また1つの学校から3作品が入賞するのは、極めて稀なことです。どんな取り組みをしているのですか』と反対に取材をされました。それから6年連続で入賞を果たし、何度か上位の賞もいただいています」(林校長)


生徒の自立心を養い、細やかな学習指導で高い学力を形成
2018年度から同校は、探究科の授業と同時に、教科横断型授業(コラボ授業)にも取り組んでいる。導入理由について林校長は、次のように話す。「探究科と同じで、学びが教科の枠に収まってしまうと、『何のために国語を学ぶのか、数学は何に役に立つのか』などと、学びに対する考えが狭まります。そうしたことから、違う教科を組み合わせた授業を行うことにしたのです。たとえば、社会×音楽のコラボ授業では、イタリアのバロック音楽を鑑賞し、同時にイタリアの地理などを学びます。そうすることで、鑑賞にも深みが増します。また、数学×美術では、数学の黄金比が調和のとれた美しさにつながっていることを学習し、実際に感じ取っていきます。学びというのは、それぞれの教科に分かれているのではなく、関連しているのだと体得すれば、日々の学習にも意欲が湧くのではないでしょうか。中学校という時期だからこそ、枠にとらわれない学びが大事で、それがより専門分化していく高校や大学のベースになると考えています」
また同校は、生徒が自学自習の習慣を確立するために、オリジナルの「自主学習プランノート」や「自主学習ノート」を活用している。「本校は、宿題を出さない学校です。自分に合う学習の仕方はそれぞれ異なるので、一律に課題を出しても意味がありません。自主学習プランノートには、1週間分の家庭学習を自分で計画し、理解度に合わせてプランを変更したり、自分自身で学習の管理をします。また、定期テストの2週間前には範囲が出るので、得意な教科と苦手な教科の時間配分をどうするかなど、テストまでの過程を自分で決めて実行します。まさにPDCAサイクルを回して、学力の向上を目指しているのです」(林校長)
そして、生徒たちは15歳で自分の進路を決め、全員高校へ進学をする。受験対策も学校が行い、3年生になると週3回、放課後に2時間、全員参加の「特別進学学習」を実施。10人前後の少人数グループで、弱点の補強や過去問の分析、面接や小論文の対策など、個々の志望校に応じて細やかに指導し、長期休暇中も講習を開いている。林校長は、「生徒の生活面まで熟知している教員が、志望校選びの相談も含め、丁寧に進学をサポートしていることが、良い結果につながっている」と分析している。実際、同校は毎年、最難関・難関校の高い合格実績をあげている。
「生徒たちが高い学力を形成しているのは、一人ひとりが非常に高いウェルビーイングを保てる環境の中で、自分で学習を管理するなど、自立をしていることも大きいですね。また、インクルーシブ教育というのは、自立した集団があって初めて成立するものです。ですので、むしろ定型発達の子を丁寧にみていくことが大事だと考えています。そして、将来、生徒たちには、障がいの有無にかかわらず表通りを歩いていけるような、多様な個性を抱えた人がみな生きやすい社会を作ってほしいと願っています。この学校で過ごしたからこそ、どんな職業に就いても、そのことを考え続けてくれるのではないかと期待しています」(林校長)
<取材を終えて>
考え方が柔軟で、心身共に大きく成長する中学校時代に、インクルーシブな環境で過ごすことは、生徒たちの人格形成にとても有益だと思う。また同校は、高校を併設していないこともあり、伸びる時期にしっかり伸ばす教育を実践している。なかでも探究科の学習は、中高一貫校であれば高校で行うような内容である。高い学力を養い、進学実績を出しているのも、詰め込みではなく、生徒自らが努力し、頑張ったことを認める環境があるから。それもインクルーシブ教育の影響が大きいのだろう。