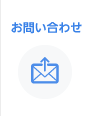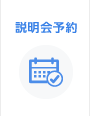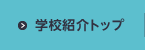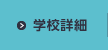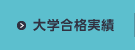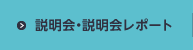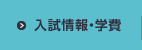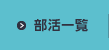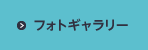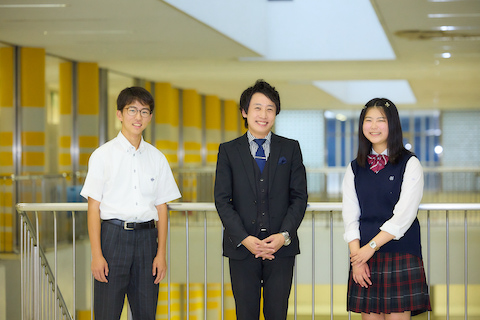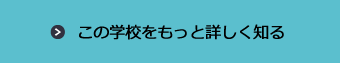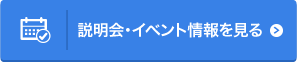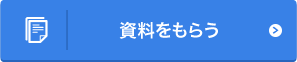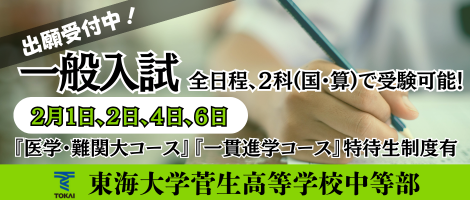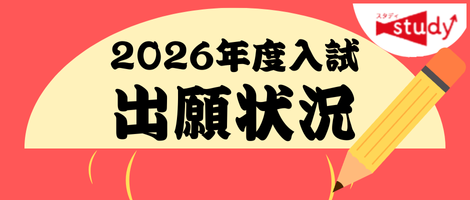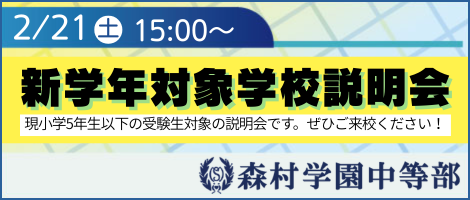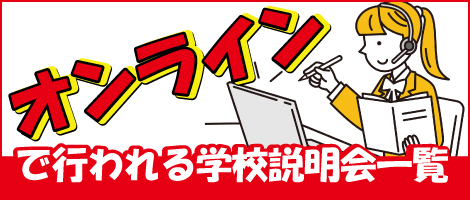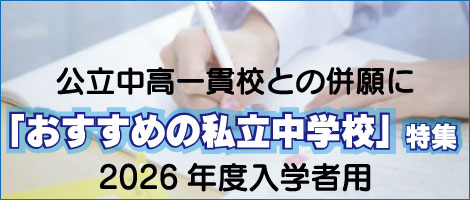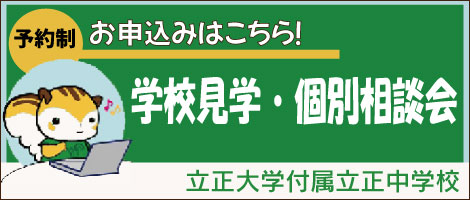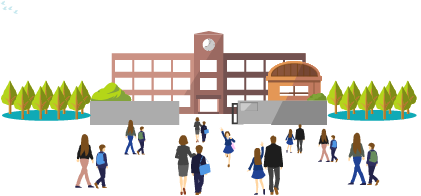スクール特集(桐蔭学園中等教育学校の特色のある教育 #10)

それぞれが胸を張れる進路を実現! 共学1期生が描いた「ありたい自分」
2019年度に共学化し、2025年3月に共学1期生が卒業した桐蔭学園中等教育学校。「将来の自分のあり方」にフォーカスした6年間の学びによる進路実現について取材した。
2019年度から共学の進学校としてリスタートした桐蔭学園中等教育学校は、今年3月に共学1期生が卒業。「アクティブ・ラーニング型授業」「探究(未来への扉)」「キャリア教育」を3つの柱として「将来の自分のあり方」にフォーカスした6年間の学びをふり返りつつ、「新しい進学校」としての進路実現について校長の玉田裕之先生に話を聞いた。
2025年3月に共学1期生が卒業
同校は共学化を機に、「アクティブ・ラーニング型授業(AL型授業)」「探究(未来への扉)」「キャリア教育」を3つの柱として掲げ、「新しい進学校」を目指した教育を行ってきた。今年3月に共学1期生が卒業し、合格実績として現役での東大5人、国公立医学部7人、現浪合わせて医学部51人といった数字が出た。しかし、同校がこの6年間で目指してきた進路実現は、そのような集計の仕方では表せないという。
「本校では5年次のプレゼン型三者面談で、生徒自身が自分の将来像について教員と保護者に語り、そこにつながる志望大学を目指すというステップを踏んでいます。結果として約5割の生徒がMARCH以上の大学に合格できましたが、それ以外の大学に合格した生徒も含めて、すべての生徒が自分の将来を語って選んだ進学先です。MARCH以上に行けなかったからといって、いわゆる負け組という気持ちを持たず、胸を張って進学しています。それが、6年間かけて行ってきたキャリア教育の成果だと考えています」(玉田校長先生)
例えば、プレゼン型三者面談で「パイロットになりたい」と語った生徒は、桜美林大学航空学群フライト・オペレーションコースに進学。「チーム医療の一翼を担う診療放射線技師として患者をサポートしたい」と語った生徒は、東京都立大学健康福祉学部放射線学科に進んだ。探究で取り組んだ論文で放射線について深く調べたからこそ、そこまで明確に「ありたい自分」を描くことができたのだ。
「進学先が第1志望ではなかったとしても、それぞれが描いた『ありたい自分』に向けた進路実現ができたのは、偏差値による大学の序列化という『新しい時代の教育』と矛盾する価値観を生徒に持たせない6年間だったからです。生徒たちは、探究を通して世の中の課題を考え、キャリア教育を通して自分の個性を見つめました。そして、見えてきた個性を活かして社会で生きていくために、どのような形で社会と接続できるのかを考えました。そこに、『偏差値65以上の大学』などという価値観が入ってくる余地はないのです。共学1期生が6年生になるときに、従来型の受験指導をしないように明言して教員たちの意思統一をしました。教員たちは、従来の進学校としてのノウハウも知っています。しかし、6年生になった途端に従来型の指導をしてしまったら、それまでの5年間が嘘になってしまうのです。ですから5年間やってきたことをそのまま大学受験につなげ、6年生の大学受験指導も『生徒が話す』というスタイルで行ってきました」(玉田校長先生)

▶︎玉田裕之校長先生
選抜方法を決めるのも生徒主体
近年、大学入試で求められる力も変わりつつあり、総合型選抜や学校推薦型選抜といった年内入試の割合が増えている。同校の場合、どの選抜で受験するかを選ぶのも生徒自身だという。
「プレゼン型三者面談の準備をする際には、『ありたい自分』につながる大学を選び、どのような選抜方法があるか自分で調べておかなければプレゼンとしては失格です。これまでの学びや課外活動などをふり返り、探究の授業でまとめた論文を活かして総合型選抜で勝負したいという生徒もいます。成績のバランスを考えて、指定校推薦で受験したいと考える生徒もいるでしょう。勉強より部活動に力を入れてきた生徒は、評定平均が影響しない一般選抜の方が力を発揮できると考えるかもしれません。どのような選択をしたとしても、自分で考えるから受験に向かうエンジンとなるのです。教員や親から言われるのではなく、生徒主体で動くことが大切なので、教員はあえて我慢して見守ります」(玉田校長先生)
プレゼン型三者面談は、準備としてワークシートに沿って「将来の自分のあり方」に関する自分の考えを整理。それをもとに10分程度のプレゼンをした後に、保護者や教員が内容を深める質問をする。
「5年生になっていきなりプレゼン型三者面談をやろうとしても、うまくいかないでしょう。本校では、1年次からAL型授業を通して自分を主語とした学びを積み重ねています。定期考査後に成績表を渡す際にも担任か副担任と面談をしますが、そこでも主体となるのは生徒です。キャリア教育の一環として、1年次から朝のホームルームなどで毎日1人ずつ『1分間スピーチ』を行い、『将来の夢』や『いま一番夢中になっていること』などについて発表もしています。本校が作成した6年間のロードマップは、『ありたい自分』を問い続け、5年次の三者面談で自分の将来を語って自分で進学先や選抜方法を選べるように設計されているのです」(玉田校長先生)

▶︎プレゼン型三者面談
6年間のロードマップ
1年「出会う」
新しい学校・友人・先生・教科・部活動と出会い、中等生としての生活の基盤を作ります。中等生としての自分と出会います。
2年「広げる」
後輩と出会い、先輩としての自分と出会います。いろいろなものにチャレンジして興味を広げていきます。
3年「見つめる」
世界・社会の中での自分を見つめるとともに、さまざまな角度からものごとの本質を見つめます。
4年「深める」
自分なりの視座から世界をとらえ、深い問題意識を作ります。自分のキャリアアンカーを意識し、それを深く下ろしていきます。
5年「仕上げる」
学校行事・委員会活動・部活動などさまざまな場面でリーダーシップを執ります。修学旅行を通じて学校生活の仕上げを目指します。
6年「飛び立つ」
この学校で学んだことを自分の将来と結びつけ、若き鳳凰として大空に飛び立ちます。

「キャリア教育」によって伸びる力
同校の進学に対する考え方が変わってきたことは受験生の保護者にも浸透しつつあるが、保護者の側の価値観も刷新してきていると感じられるという。
「共学1期生の保護者の中には、従来の進学指導を期待している方もいました。ですから共学1年目は、保護者の皆さんと本校が目指すキャリア教育とは何かというディスカッションなども行いました。しかし2年目以降は、子どもたちが成長し、自立していく様子を間近で見て、最終的には満足して卒業を迎えた方が多かったと感じています。仕事を持つ方は、自分の職場でどんな若者と一緒に働きたいか考えたときに、本校が何を目指しているかを理解していただけたのだと思います」(玉田校長先生)
「キャリア教育」で大きく伸びる力の1つとして、注目したいのがメタ認知だ。
「自分を客観的に評価することができるからこそ、自分の個性を知り、『ありたい自分』を描くことができます。人の役に立ちたいといっても、医師に向いている生徒ばかりではありません。例えば、人の役に立つために地方公務員を目指す生徒もいました。高齢者をはじめとする地域の人のために働きたいという優しさも、才能の1つなのです。彼はそのことに気づけたので、地方公務員を目指して祖母の出身地でもある信州大学に進学しました」(玉田校長先生)

それぞれが描いた「ありたい自分」に向かうための進路実現
「将来の自分のあり方」にフォーカスした6年間の学びによって、これまでの桐蔭学園とは異なる多様な進路が見えてきている。例えば、麻布大学獣医学部に学校推薦型選抜で合格した生徒は、産業動物獣医師を目指しているという。
「獣医学部を目指す場合、犬や猫が好きだから獣医師になりたいという生徒が多いと思います。しかし彼女が描いた『ありたい自分』は、そういった獣医師ではなく産業動物獣医師でした。畜産センターなどでは、出荷前の品質管理をするためにも獣医師が重要な役割を果たします。彼女は桐蔭横浜大学の教授のもとで、共同研究に参加したり、麻生大学のプロジェクトに早くから強い関心を示したりしていました。そのようにして、徐々に、産業動物獣医師という職業に興味を持っていったようです」(玉田校長先生)
初の卒業生となった共学1期生の約8割は、それぞれが胸を張って「ありたい自分」に向けて歩みを進めている。一方で、約2割の生徒は現役合格できなかった。しかしそれは、「ありたい自分」をしっかりと描き、それを貫き通したからこその結果とも言える。
「現役合格できなかった生徒の多くは医学部を目指しているので、簡単に諦めて他の学部を目指すことはできなかったのです。医学部以外を目指す生徒であっても、合格するために同一大学の複数学部に出願したり、合格しやすい学部を選ぶような受験はしていません。就きたい職業につながる学部、学びたい教授がいる学部といった明確な目標があり、そこに入りたいという意志も固いのです。この6年間を踏まえた次の目標として、『ありたい自分』への思いを貫きつつ全員が現役合格できることを目指していきたいと考えています」(玉田校長先生)

▶︎産業動物獣医師を目指し、麻布大学獣医学部に学校推薦型選抜で合格した生徒は、在学中に日本動物学会議の関東支部大会にも参加
「新しい時代」に必要な力は大学受験にも通じる力
2022年4月に同校の校長に就任した玉田先生は、1989年に桐蔭学園で国語科教員として勤務を始めて以来、高等学校男子部、中等教育学校(当時は男子校)で数々の卒業生を送り出してきた。
「担任や学年主任として生徒を指導していた当時は、従来型の受験指導を行っていました。その中で、高2ぐらいで将来のことや受験勉強のやり方、選抜方法などについて自分から話し始めた生徒は、受験に強いと感じていました。それをプログラムとして確立させたのが、本校のキャリア教育です。従来の講義型授業でも、生徒の発言をきっかけに議論が展開され、そこから授業が面白くなっていき、多くの学びがあったという経験もあります。今思うと、そこにAL型授業の原型があったように感じます。本校が作成した6年間のロードマップにあるプログラムは、受験にも強いと思っています。ですから、新しい時代に必要な教育と大学受験に向けた教育を区別することなく、一体化したものととらえています」(玉田校長先生)
桐蔭学園は50周年を迎えた2015年に、「自ら考え判断し行動できる子どもたち」を育むという新しい教育ビジョンを打ち出し、AL型授業を導入。新しい教育ビジョンに合わせて、校則や学園祭のあり方などを見直すことも、タスクチームを作って進めている。校則をはじめとする学校づくりに関して、生徒が自分たちの希望を出していいということも教員と生徒の間で共有されている。
「校則については、従来は管理するような文面だったものを生徒が主語になるような書き方に変えています。生徒たちの希望をまとめて、私に伝える機会も作っています。今日もこの後、生徒たちが通学用バックパックの改善に関して業者と話し合ったことを伝えに来る予定です。『新しい進学校』としてのカタチは整ってきましたが、生徒たちによる『学校づくり』は今後も続けていきたいと考えています」(玉田校長先生)

卒業生を通したロードマップのふり返り
学力試験以外の新しいタイプの入試への対策は、特に必要なかったという。生徒たちは日頃から話すことに慣れているので、特別に面接の練習をしなくても合格できた。グループワークもたくさん経験しているので、グループ面接が得意な生徒も多い。「傾聴と承認」の大切さも学び、自分の意見ばかり言うのではなく、相手の発言を聞く姿勢もできているので、受験前に集中的に対策をする必要もなかったのだ。
「探究で取り組んだ論文は、自分の好きなことを突き詰めて形にしているので、その内容を志望理由書にも活かすことができます。本校の論文はコンクールに出すために書くものではないので、それ自体が成果物として合格につなげられるようなレベルではありません。全員の論文それぞれが尊いものなので、優劣をつけるような評価は行っていないのです。しかし、志望理由を語る際の大きな強みになります」(玉田校長先生)
共学1期生が卒業し、6年間のロードマップをふり返って検証することが可能となった。大学生となって楽しく充実した日々を過ごしている卒業生の様子から、現時点での成果も実感できる。しかし、ロードマップに記されたプログラム全体の成果が検証できるのは卒業生が社会に出てからであり、長いスパンが必要になるだろう。
「本校では、従来の進学校が行ってきた受験意識の前倒しと競争の喚起をやめました。大学受験に関する技術的なことを意識するのは5年生になってからで、4年生までは前倒ししません。6年間の道筋はすべてロードマップに記してあるので、思いつきで低学年の生徒に向けて、東大に合格した卒業生からホームルームで話を聞くようなこともしません。それぞれのプログラムの内容や実施する時期には意味があるのです。共学1期生が入学するときに、教員や生徒、保護者とビジョンを共有して、同じ方向を向いて進んできました。6年経って『新しい進学校』としてのカタチが整った今、1つ1つのプログラムの目的を忘れて形骸化しないように、基本に立ち返ることが大切だと考えています。時期が来たから実施するのではなく、何を目的に行うのかなど、常に基本を忘れないことが今後の課題だと思っています」(玉田校長先生)
<取材を終えて>
2023年に共学1期生(5年生)に取材したAさんは、文系を幅広く学べる青山学院大学総合文化政策学部に進学したそうだ。卒業後もチューターとして同校を訪れ、後輩たちに6年間のふり返りなどを伝えているという。2024年に取材したAさんは慶應義塾大学環境情報学部、Kさんは秋田大学医学部に進学し、それぞれの「ありたい自分」に向かって歩き始めた。合格実績として発表されている数字だけでなく、それぞれが描いた「ありたい自分」にも注目していただきたい。
参考記事
2023年取材
受験勉強もPBL型!共学化5年目に見えてきた「新しい進学校」のカタチ
2024年取材
「ありたい自分」を宣言!キャリア教育の一環として行う「プレゼン型三者面談」